風神雷神
(栄西 と 建仁寺)
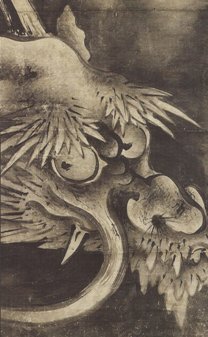 子どもの頃、教科書で 「 風神雷神 」 の屏風図を見て、子ども心に どうして
「 青鬼 」 と 赤鬼でなく 「 白鬼 」 だろうと思ったものです。
子どもの頃、教科書で 「 風神雷神 」 の屏風図を見て、子ども心に どうして
「 青鬼 」 と 赤鬼でなく 「 白鬼 」 だろうと思ったものです。
その国宝 「 風神雷神 」 が、 「 開山・栄西禅師 800年遠忌 特別展
” 栄西と建仁寺 ” 」 として、東京国立博物館平成館 で展示されました。
展示会の 目玉 は、勿論 「 風神雷神 」であり、 「 雲龍図 」
でした。
「 雲龍図 」 は、建仁寺の方丈にありましたが昭和9年(1934)の室戸台風で
方丈が倒壊したため、現在では50幅の掛け軸に改装され京都国立博物館に
保存されています。
そんな訳で、建仁寺の方丈の一室には海北友松の作品に代わって精巧な
複製画が はめ込まれているそうです。
右写真 : 安土桃山時代の巨匠海北友松の傑作 「 雲龍図 」 の目玉 (一部) です。
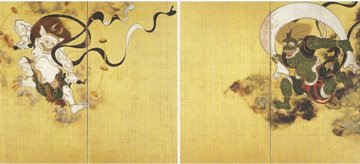 ◎ 風神雷神 ◎
◎ 風神雷神 ◎
「 風神雷神 」 は、建仁寺を代表する宝物として教科書などでよく知られた
江戸時代に活躍した 「 俵屋宗達 」 の作品です。
風神は風、雷神は雷・雨の神であり、自然を神格化したものといわれます。
そろぞれ別の発生をしたようですが、二神は組み合わされて護法神となり、
さまざまな仏教絵師によって描かれています。
鎌倉時代以降に描かれた 風神雷神 では、画面上部の右に雷神、左に風神が
配されたものが多く、雷神は赤く、風神は緑で描かれているそうです。
しかし、宗達の 「 風神雷神 」 は、宗教性はなく、仏画の通例と異なり、
画面に明るさと軽やかさをもたらすために、雷神の肌を儀軌にある 赤 から
白色 に改めています。
また、筋肉の隆起した量感ある体を支える雲は、墨、胡粉、銀などを滲ませ
て形をはっきりとさせていません。 それによって金地の光の中に二神が
ふわりと浮かんでいるように表現されています。
この天空に舞う姿を、スピード感があると見る人、のんびりと楽しげに遊ぶ
姿と見る人、さまざまな自由さのある作品と思います。 因みに、私は
天空で 楽しそうに四季を司る 鬼さんたち と思えます。
右写真 : 俵屋宗達筆 「 国宝風神雷神図屏風 」 です。
 ◎ 栄西 (ようさい) 禅師 ◎
◎ 栄西 (ようさい) 禅師 ◎
栄西禅師 (1141〜1215) は日本に禅宗を広め、建仁2年(1202)に禅寺
建仁寺を開創しました。
現在の岡山県に生まれた栄西は、13歳で比叡山延暦寺に登り、天台・
密教を修め、さらに仏教教学を深く学ぶため宋に渡りました。
47歳のときに再び宋に入り、臨済宗黄龍派の禅を学びました。帰国後、
博多に招福寺を開き、正治2年(1200)に鎌倉に寿福寺を、その2年後
には将軍源頼家の庇護のもと京都に 建仁寺 を開いて禅の精神を広めて
いきました。
更に、宋から持ち帰った茶種を栽培し、茶の効用と作法を説き、茶祖
としてもその功績が称えられています。
右写真 : 建仁寺・開山堂にある 栄西禅師坐像 です。
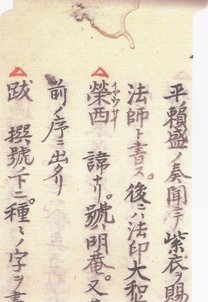 栄西禅師は、 (えいさい) あるいは (ようさい) と呼ばれています。
栄西禅師は、 (えいさい) あるいは (ようさい) と呼ばれています。
古くから両方の読み方があったのですが、今回展示会では (ようさい)
と称されていました。
その根拠は、江戸時代の建仁寺335世高峰東峻(1736〜1801)が、
その主著で (イヤウサイ) とふり仮名を付けて示し、以降
建仁寺の文化の一つと成っています。
右写真 : 興禅護国和解の部分にある (イヤウサイ) の表現です。
 トップページに戻ります。
トップページに戻ります。
 トップページに戻ります。
トップページに戻ります。